お酒好き必見!サプリメント成分おすすめガイド【14選】
2024.08.06
2024.11.12
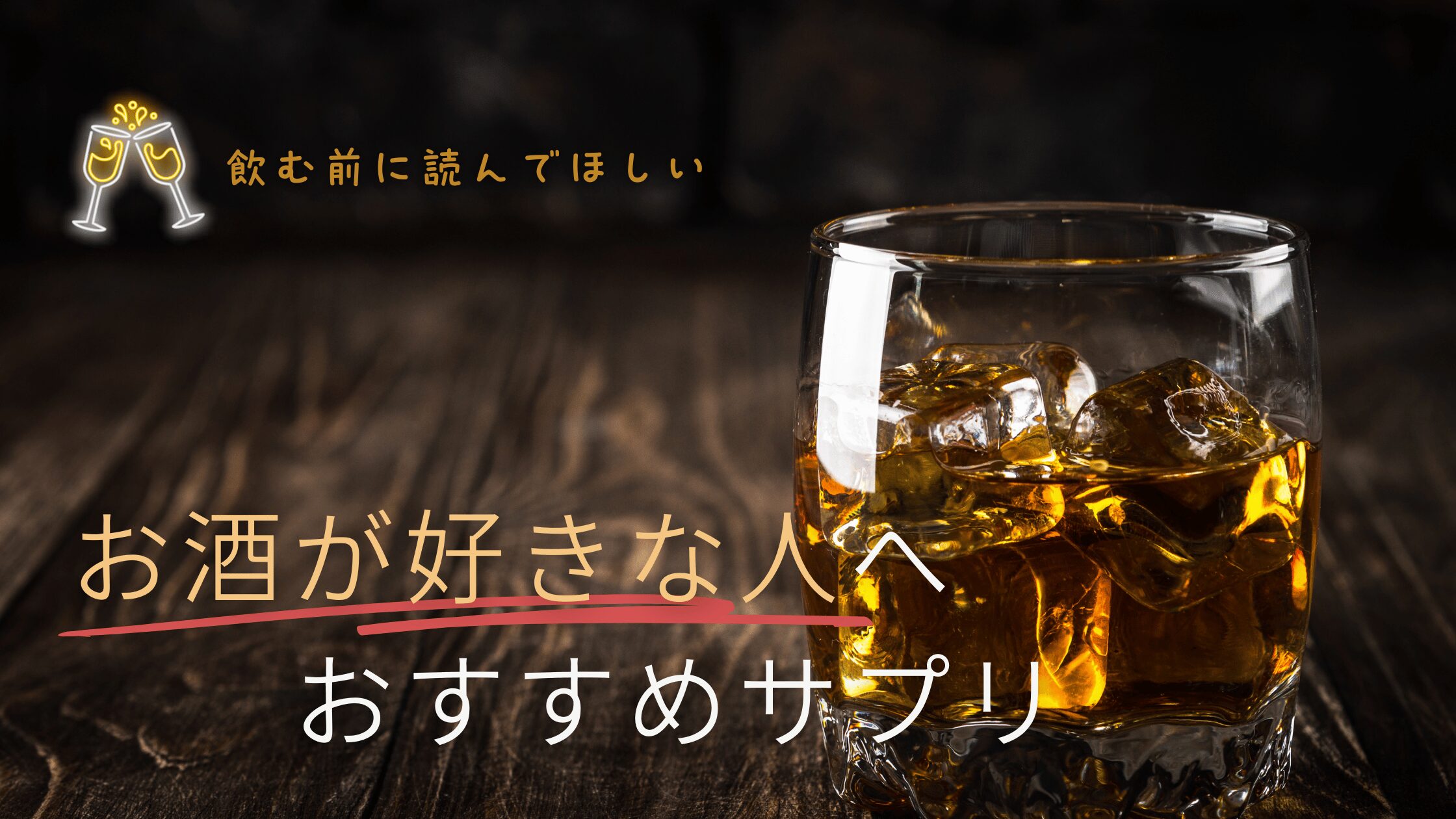
お酒が美味しくてつい飲み過ぎてしまうこと、誰にでもありますよね。
しかし、飲みすぎは翌朝の二日酔いだけでなく、肝臓への影響も心配です。
飲み会前にウコンを摂る方もいらっしゃると思いますが、どれだけ効果があるのでしょうか?
そこで、お酒好きな方におすすめのサプリメント成分をご紹介します。
- 肝臓に良い成分
- アルコール分解を促す成分
それぞれ詳しく解説していきますので、お酒をよく飲む方はぜひ一度チェックしてください!
Contents
おすすめの成分

1. ビタミンB1
ビタミンB1は、エネルギー代謝に大きく関与しているビタミンです。
お酒を多く飲む人では不足する可能性があるため、サプリメントで補給するのが良いでしょう。(1)(2)
ただし、水溶性ビタミンであるビタミンB1は過剰に摂取しても尿中に排泄されてしまいます。
「たくさん摂れば良い」というわけではないことに注意が必要です。
2. ビタミンB2
ビタミンB2は、主に脂質の分解に大きく関わるビタミンです。
脂質代謝は肝臓で活発に行われるため、肝臓がアルコールを分解する時には脂質代謝が滞る可能性があります。
そのため、日頃から大量に飲酒する方は通常よりも脂質が代謝されにくく、結果として脂肪肝などに繋がりやすくなります。
また、慢性的にお酒を飲む方の場合、ビタミンB2が腸から吸収される量が減ったり、腎臓で再吸収されにくくなるリスクが指摘されています。(3)
これらの理由から、お酒が好きな人はビタミンB2のサプリメントを使ってみても良いかもしれません。
ビタミンB1と同様に水溶性ビタミンですので、過剰な分は尿中に排泄されてしまう点に注意しましょう。
3. ナイアシン
ビタミンB群の一種であるナイアシンは、アルコール分解酵素であるアルコール脱水素酵素(ADH)やアルデヒド脱水素酵素(ALDH)の補酵素(酵素の働きを助ける成分)として働きます。
お酒をよく飲む人では消費量が増え、通常よりも必要量が増えることがありますが、基本的には不足しにくい成分です。
また、ナイアシンの摂取はアルコール依存症に効果があるとする報告もあります。
ナイアシンのサプリメントには「ニコチン酸」と「ニコチン酸アミド」をはじめとする、いくつかの種類があります。
ニコチン酸は効果が強い反面、ナイアシンフラッシュ(ホットフラッシュ)と呼ばれる、一時的な肌の紅潮や痒み症状がよく起こります。
ニコチン酸アミドはナイアシンフラッシュが起こりづらいですが、ニコチン酸よりも効果はマイルドです。
ただし最近の研究では、過剰なナイアシン摂取で生じた代謝物が、心血管の有害事象と関連することが報告されています。(4)
サプリメントでの摂りすぎには注意が必要です。
4. 亜鉛
亜鉛は、アルコール脱水素酵素(アルコールを分解して酢酸へ変える酵素)の構成に必要な微量元素です。
飲酒量が多いとアルコール脱水素酵素が大量に必要となるため、必要な亜鉛の量も多くなります。
また、お酒をよく飲む人は小腸での亜鉛の吸収量が減少することがあります。
こうした理由から、飲酒量が多い人はサプリメントで亜鉛を補給することも考えられます。
ただし、亜鉛と相性が悪い薬もあるので、使う前に医師や薬剤師へ相談しましょう。
また、長期間使い続けると体内で銅が不足する可能性があります。摂りすぎには気を付ける必要があります。
この他に、薬やサプリメントで鉄分を摂取している人も注意が必要です。
亜鉛と鉄分は小腸で同じ経路を通って吸収されます。鉄分の摂取量が多い場合、亜鉛の吸収量が低下する可能性があります。
ウコンの製品にも鉄分を多く含んでいるものがありますので、両方使いたい場合には摂るタイミングをずらすなど、使い方に気をつけましょう。
5. システイン
システインには、アルコール分解酵素であるアルコール脱水素酵素やアルデヒド脱水素酵素を活性化する作用が知られています。
食品から摂取できる量は少ないため、サプリメントを利用するのが効率的です。
ただし、血糖値をコントロールするインスリンの分泌に、L-システインが悪影響を与える可能性が報告されています。(5)
糖尿病治療をしている方や危険性のある方は摂取を控え、そうでない方も摂りすぎに注意する必要があります。
6. メチオニン
メチオニンは必須アミノ酸の1つで、人の体内で十分な量を作れないため、食事などから摂取する必要のあるアミノ酸です。タンパク質の合成や脂肪分解など、身体にとって重要な多くの反応に関わっています。
また、抗酸化作用をもつグルタチオンの産生にも関与しています。
飲酒時には消費され減少してしまうため、飲酒習慣がある人はサプリメントで補うこともおすすめです。
ただし、メチオニンの過剰摂取は非アルコール性脂肪性肝疾患に関与していると示唆している報告もあります。(6)
また、メチオニンの代謝産物であるS-アデノシルメチオニン(SAMe)が、体内時計により駆動される生体リズムを障害するという報告もあります。(7)
こうした理由から、サプリメントの摂りすぎには注意する必要があります。
7. イノシトール
イノシトールは抗脂肪肝ビタミンとも呼ばれ、肝臓に脂質が溜まりにくくするなど、肝機能の維持に重要な働きをしています。
体内で糖質(グルコース)から合成されますが、その合成量には上限があります。
基本的には日常生活で欠乏しにくい成分ですが、お酒をよく飲むので肝機能には気をつけたい、という方はサプリメントを試してみてもいいかもしれません。
8. ウコン
ウコンは春ウコン、秋ウコン、紫ウコンなどの種類が知られており、それぞれ異なった成分を持っています。
一般的に、サプリメントでは秋ウコンが利用されており、その中に含まれるクルクミンという成分が主な作用をもちます。
ポリフェノールの一種であるクルクミンには、ポリフェノール共通の抗酸化作用のほか、肝機能を高める作用があります。
これらの作用が、飲酒によって生じる酸化ストレスを和らげ、肝臓でのアルコール分解を促します。
一方で、ウコンの長期使用や過量摂取をおこなった場合、反対に肝障害を引き起こす危険性があります。
また、秋ウコン製品によっては鉄を多く含有しているものがあります。過量な鉄分摂取は肝障害の原因となる可能性があり、これも注意すべきポイントです。
使用は一時的なものに留め、継続摂取しないように気をつけましょう。
9. オオアザミ
マリアアザミやミルクシスルという名でも知られているハーブのオオアザミは、古くから肝臓疾患に利用されてきました。
ドイツでは種子を用いたハーブティーが胆汁分泌の機能障害に用いられているほか、オオアザミに含まれる成分を利用した医薬品が肝臓病に対して認可されています。
比較的安全性が高いとされていますが、キク科のハーブであるため、キク科アレルギーの人は使用を避けましょう。同じキク科であるヨモギやブタクサなどの花粉症がある人は注意が必要です。
10. プラセンタ
プラセンタは、胎盤から抽出された成分です。
多くの成分が含まれているため詳しい仕組みは明らかになっていませんが、慢性的な肝疾患に対して医療の現場で点滴として使われている薬もあります。
また、化粧品として使われていることでも有名です。
サプリメントの場合、飲むタイプで商品化されているものがあります。
少しでも肝臓に良い可能性のあるサプリメントを使ってみたい!という方は試してもいいかもしれません。
11. β-クリプトキサンチン
β-クリプトキサンチンは、抗酸化作用を持つカロテノイドの一種です。
アルコールを大量に摂取すると、体内で活性酸素という物質が生じます。活性酸素は様々な細胞に対して障害を与えることがわかっており、肝障害など多くの疾患リスクにつながります。
抗酸化物質には活性酸素を除去し、細胞を保護する効果があります。
カロテノイドは脂溶性のため吸収も良く、適度な摂取は肝臓などの保護に役立つ可能性があります。
12. オルニチン
「お酒を飲んだ後はシジミ汁が良い」と、昔からよく言われるほど日本人に浸透しているお酒とシジミの相性。
その理由の1つとして、シジミに含まれるオルニチンの効果にあると言われています。
アミノ酸の一種であるオルニチンは、肝臓で有害なアンモニアを無毒な尿素へと変換する役割を持っています。
お酒を飲むと、肝臓でアルコール代謝が行われる結果、エネルギー産生の邪魔をしてしまいます。
オルニチンを摂取することで、アンモニアから無毒な尿素への変換が促進され、結果として肝臓で行われるさまざまな反応がよくなり、エネルギー産生の効率も上がることが期待されます。
ただし、食品中に含まれるオルニチンは微量なため、サプリメントで摂取するのが効率的です。
13. セサミン(胡麻)
胡麻に多く含まれるセサミンには、血液中のアルコール濃度低減作用(8)や、肝臓でのアセトアルデヒド脱水素酵素を増やす作用をもつことが動物実験で報告されています。(9)
食品からはわずかしか摂取できないため、十分な量を摂取するには大量に食べる必要があります。
しかし、胡麻はセサミンを多く含んでいる一方、高カロリーのため摂りすぎに注意が必要です。
効率よく摂取するにはサプリメントが望ましいでしょう。
14. 酢酸菌
近年、酢酸菌がもつ様々な働きが注目されています。その1つがアルコールを分解する役割です。
スーパー等で売られているお酢は、アルコールを酢酸へ変換することで作られていますが、この時に関わっているのが酢酸菌のもつアルコール分解酵素です。
この酵素は肝臓がアルコールを分解するために持っている酵素と同じものです。
そのため、酢酸菌を摂取することでアルコールが肝臓にたどり着く前に分解されるようになり、肝臓の負担軽減が期待できると言われています。(10)
酢酸菌はにごり酢などに含まれていますが、市販されている澄んだお酢は酢酸菌が除去されているため注意が必要です。
お酢が苦手な人や手軽に摂取したい場合には、サプリメントの利用が効率的でしょう。
まとめ

お酒が好きな方は無視できない肝臓への影響。
少しでも負担を減らすためには、肝臓に良いサプリメントを摂取してみてもいいかもしれません。
ただし、それぞれのサプリメントごとに注意すべき点はありますので、必ずチェックしてくださいね。
また、アルコールを毎日嗜んでいるような方の場合は、休肝日を設けることも大切です。
週に2回以上は休肝日を設けるように心がけましょう。
肝臓への影響と上手に付き合いながら、適度な飲酒を意識した生活をお送りください!
参考文献
(8)“肝機能とゴマの稀少成分”,サントリーウエルネス,https://health.suntory.co.jp/rouka/04/kankinou.html(参照2024-08-06)
(10)“酢酸菌のアルコールに対する効果”,酢酸菌ライフ,https://sakusankin-life.jp/alcoholcare(参照2024-08-06)






